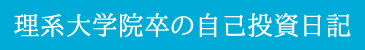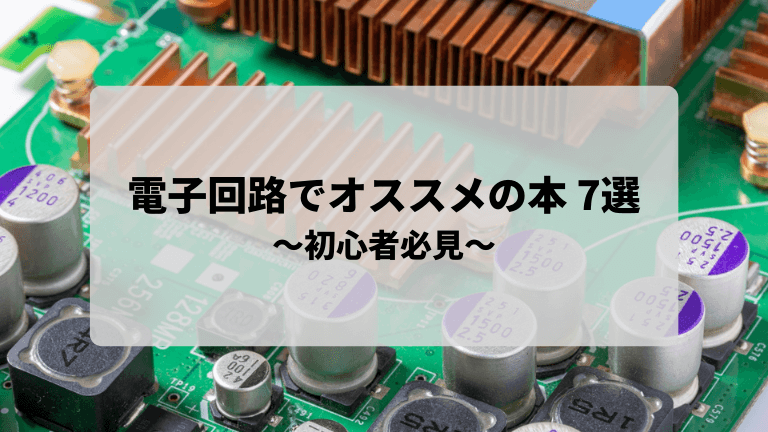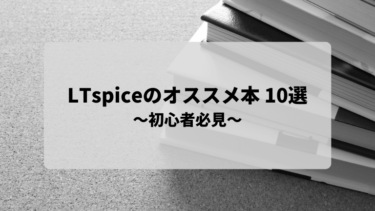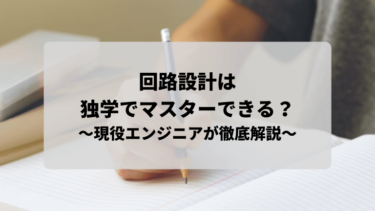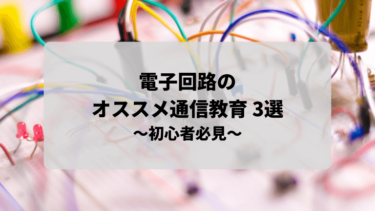回路設計ができるようになりたい。
電子回路のオススメ参考書ってどれ?
こんな要望に応えます。
回路設計入門者の中には、『どうやって勉強を進めていくべきか悩んでいる方』も多いですよね。
今回紹介する本を読めば、電子回路を体系的に学ぶことができ、順調に回路設計ができるようになります。
そこで今回は、『私自身が早く読むべきだったと感じた7冊』を紹介していきます。
・図解でわかる はじめての電子回路
・合点!電子回路超入門
・定本 トランジスタ回路の設計
・現場でわかるノイズ対策の本
・図解 つくる電子回路
・電子回路シミュレータLTspice実践入門
カラー徹底図解 基本からわかる電気回路
| 難易度 | |
| おすすめ度 | |
| 価格(参考) | 2,530円 |
この本を読むと、『電子回路の動作イメージ・理論』を習得することができます。
特に、基本部品である「抵抗・コンデンサ・コイル」の理論・動作説明が分かりやすいです。
「コンデンサ・コイルについて、完璧に理解出来てないかもしれない…」
以上のように自信がない方は、トランジスタなどを勉強する前に、まずはこの1冊で基礎を固めましょう。

基本的な電子部品の動作を理解できれば、後に学ぶトランジスタ等も理解しやすくなります。
\電気回路から学びたい方はこちらへ↓/
困っている人 電気回路を勉強しなくちゃいけない。 オススメの参考書ってどれ? こんな要望に応えます。 電気回路初心者の中には『どうやって勉強を進めていくべきか悩んでいる』という方も多いですよね。 […]
図解でわかる はじめての電子回路
| 難易度 | |
| おすすめ度 | |
| 価格(参考) | 2,618円 |
『電子回路入門のバイブル』とも言える一冊です。
電子回路の基礎である「9つの内容」が、完結にまとめられています。
・計算と回路の基本
・ダイオード
・トランジスタの基本
・オペアンプ
・2進数と16進数
・論理回路
・パルスと発振回路
・モータ制御
・変調と復調
以上の内容を、『イラストでの図解も含めて解説』しています。

初めの1冊として、ぜひ「電子回路の基本」をこの本で学んでください。
合点!電子回路超入門
| 難易度 | |
| おすすめ度 | |
| 価格(参考) | 2,640円 |
『電子回路の基礎理論』を解説した一冊です。
アナログ信号を扱う場合には、基礎理論を理解していないと正しく回路設計できません。
この本を読めば、『他の参考書では難しく感じる基礎理論を着実に理解する』ことができます。
第1部 抵抗とインピーダンス
第2部 複素数とejθ
第3部 対数と時定数
第4部 積分と微分
第5部 群遅延と特性インピーダンス
第6部 フーリエ変換と畳み込み
近年、高速の通信回路が増えており、『信号処理について理解することは必須』です。
信号処理について理解するためには、基礎理論は避けては通れないため、ぜひこちらの本を読んでみて下さい。

できるだけ分かりやすい基礎理論の本を探している方にオススメです。
定本 トランジスタ回路の設計
| 難易度 | |
| おすすめ度 | |
| 価格(参考) | 2,350円 |
『トランジスタ回路の設計方法』を紹介している本です。
各素子の定数を決める順番や、その理由についても大変分かりやすく解説してくれています。
第1章 トランジスタ回路への誘い
第2章 増幅回路を動かす
第3章 出力を強化する回路
第4章 ミニパワーアンプの設計・製作
第5章 パワーアンプの設計・製作
第6章 周波数特性をのばすには
第7章 ビデオ・セレクタの設計・製作
第8章 カスコード回路の設計
第9章 負帰還増幅回路の設計
第10章 直流安定化電源の設計・製作
第11章 差動増幅回路の設計
第12章 OPアンプ回路の設計・製作
トランジスタの型番なども記載されているため、本を読みながら自分で実際に設計してみることもできます。
私の場合は、『設計した回路をLTspice(無料のシミュレータ)に反映して動作確認』しました。

設計方法を解説している本は少ないため、貴重な1冊です。
現場でわかるノイズ対策の本
| 難易度 | |
| おすすめ度 | |
| 価格(参考) | 3,080円 |
回路設計で必ず課題となる『ノイズ対策法』を記した1冊です。
「ノイズ知識」と「ノイズ対策法」が基礎からしっかり解説されていました。
第1部:ノイズの基礎知識
第2部:ノイズ対策法
特に、ノイズ基礎知識について詳細な解説があるため、ノイズ初心者にもオススメです。
また、最後には『ノイズ発生回路&対策方法をLTspiceで再現する方法』が示されており、非常に参考になります。

ノイズ対策技術に関わる「電気・磁気・電磁波」の基礎知識や考え方が網羅されていました。
図解 つくる電子回路
| 難易度 | |
| おすすめ度 | |
| 価格(参考) | 1,100円 |
とても珍しい『電子回路制作のノウハウ解説本』です。
「電子部品の選定方法」から「道具の使い方」まで網羅されています。
第1章 電子回路を設計する
第2章 腕と道具をそろえる
第3章 ブレッドボードで組む
第4章 ユニバーサル基板で作る
無安定マルチバイブレータを例として、『回路の組立て方法までを筆者自らのイラストで解説』してくれています。
そのため、この1冊で「回路制作の流れ」をしっかり理解できました。
この本を読んで『実際の作業工程』を理解することによって、より良い設計ができると思います。

回路設計初心者だけでなく、回路制作未経験者にぜひ読んで欲しい1冊です。
電子回路シミュレータLTspice実践入門
| 難易度 | |
| おすすめ度 | |
| 価格(参考) | 3,080円 |
回路シミュレーションソフト『LTspice』を使用した基本部品の動作解説書です。
LCRやダイオード・トランジスタの動作を、シミュレーションで学べる点がとても良かったです。
第1章 抵抗、インダクタ、コンデンサ、トランス
第2章 ダイオード、ツェナーダイオード
第3章 トランジスタ
第4章 接合型電界効果トランジスタ
第5章 トランジスタを使った増幅回路
LTspiceの使い方も同時に学べるため、特に『シミュレーションソフト使用未経験者』にオススメです。
回路設計していく上でシミュレーションソフト使用は必須であるため、「回路動作とLtspiceの両方を学べる」のは一石二鳥となります。

Ltspiceが使えるようになると、実際に実験しなくても設計回路の動作を確認できるようになるのです。
\LTspiceに興味がある方はこちらへ↓/
困っている人 LTspiceの使い方をマスターしたい。 オススメの本ってどれ? こんな要望に応えます。 これからLTspice使用を検討している方の中には、『どうやって使い方を学ぶべきか悩んでいる方』も多いと[…]
電子回路でオススメの本まとめ

今回は、『電子回路でオススメの7冊』をご紹介しました。
・ 図解でわかる はじめての電子回路
・ 合点!電子回路超入門
・ 定本 トランジスタ回路の設計
・ 現場でわかるノイズ対策の本
・ 図解 つくる電子回路
・ 電子回路シミュレータLTspice実践入門
いかがでしたでしょうか。
回路設計は非常に難しく、心が折れるような出来事も沢山あります。
今回紹介した本を読めば、勉強のスタートダッシュが上手くいき、順調に回路設計ができるようになります。

また、下記でオススメの問題集も紹介しています。
理解を深めるために、ぜひご活用ください。
\電子回路のオススメ問題集はこちら↓/
困っている人 電子回路の問題を解けるようになりたい。 オススメの問題集ってどれ? こんな要望に応えます。 電子回路入門者の中には、『演習問題を解いていくことで理解を深めたい』という方も多いですよね。 […]
回路設計を独学でマスターしたい方に向けて

また、『回路設計を独学でマスターしたい方』も多いと思います。
結論から申し上げますと、回路設計は独学でマスター可能です。
回路設計エンジニアの多くは、独学で回路設計を学んでいます。
下記で『回路設計を独学でマスターする方法』について紹介しているため、ぜひご覧ください。

正しい手順を踏んで、効率良くマスターしていきましょう。
\独学で回路設計をマスターする方法へ↓/
困っている人 回路設計に興味がある。 独学でマスターできるの? こんな疑問を解消します。 結論から言うと、回路設計は『独学でマスター可能』です。 この記事を読めば、「独学で回路設計をマスター[…]
回路設計を通信教育で学ぶのもあり

『回路設計を通信教育で学ぶのも効率的である』ため、オススメできます。
通信教育を利用すれば、体系的に学ぶことができるため、より早くマスターできるのです。
最近は、Udemyのような安価なプログラムも出ています。
下記で『電子回路のオススメ通信教育』について紹介しているため、ぜひご覧ください。

実用的な回路を扱っているため、即戦力として活躍できるようになるでしょう。
\電子回路のオススメ通信教育はこちら↓/
困っている人 電子回路を通信教育で学びたい。 どこの通信教育がオススメ? こんな要望に応えます。 電子回路の設計者を目指している方の中には、『どうやって勉強を進めていくべきか悩んでいる方』も多いと思います。 […]
大学生・大学院生ならPrime Studentがオススメ

「Prime Student」は、Amazonプライムの学生版です。
月額300円で下記の特典が利用できます。
お急ぎ便が無料
Prime Video見放題
Prime Music聴き放題
Prime Readingで電子書籍読み放題
Amazon Photosで写真保存し放題
本最大10%ポイント還元
今回のように、書籍を購入する機会には『本最大10%ポイント還元』は必ず利用すべきです。
『無料期間が6ヶ月間もある』ため、試しに登録してみると良いでしょう。

詳しくは下記で紹介しているため、ぜひご覧ください。
\Prime Studentの特典・口コミなど↓/
困っている人 Prime Studentがお得ってよく耳にする。 入会するべきか判断するため、値段・特典・対象者が知りたい。 こんな要望に応えます。 学生の中には、『Prime Studentを利用すべきか分[…]