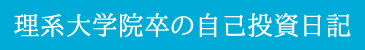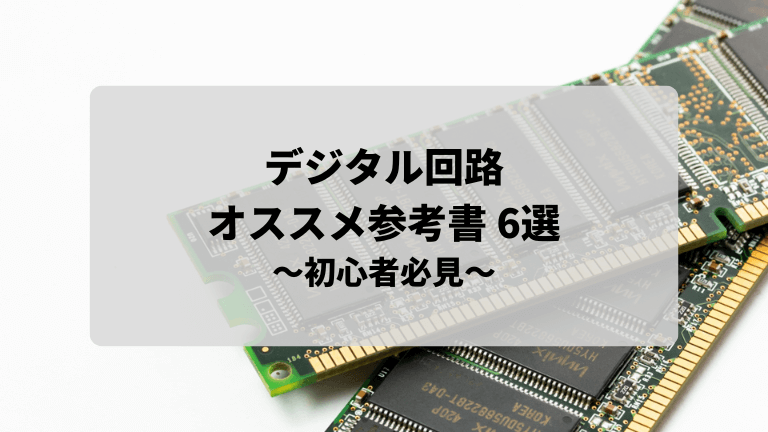デジタル回路を学びたい。
デジタル回路でオススメの参考書ってある?
こんな要望に応えます。
デジタル回路初学者の中には、『どうやって勉強を進めていくべきか悩んでいる方』も多いと思います。
今回紹介する参考書を読めば、デジタル回路を体系的に学ぶことが可能です。
そこで今回は、『私自身が早く読むべきだったと感じた6冊』を紹介していきます。
・なっとくするディジタル電子回路
・ゼロから学ぶディジタル論理回路
・ディジタル回路設計とコンピュータアーキテクチャ
・FPGAの原理と構成
・CPUの創りかた
オススメ参考書①:基本からわかる ディジタル回路講義ノート
『デジタル回路の基礎知識』を解説した一冊です。
『デジタル回路の基礎』である以下の内容が、完結にまとめられています。
・集合の概念
・論理関数
・組合せ論理回路
・順序回路
以上の内容が、『高校生でも分かるレベルで解説』されています。
ただし、『最低限の知識のみ』をコンパクトにまとめているため、この1冊だけでは『実際のデジタル回路設計』はできません。

デジタル回路の知識が全くない方が、初めの1冊として使用するにはオススメです。
オススメ参考書②:なっとくするディジタル電子回路
大学の教科書と異なり、『堅苦しい表現を使っていない解説本』です。
内容としては、以下の『基礎知識』をメインとしています。
・基本論理ゲート
・ブール代数
・論理回路
・フリップフロップ
・順序回路
・A/D変換
説明自体がとても分かりやすいため、『学校の授業で理解できなかった点』もこの参考書を読めば理解できると思います。

A/D変換の内容は少し難しいですが、他の参考書に比べれば圧倒的に分かりやすかったです。
オススメ参考書③:ゼロから学ぶディジタル論理回路
デジタル回路の基礎に加えて、『プログラミングを用いた論理回路設計』も紹介している参考書です。
なお、デジタル回路設計に必須のプログラミング言語『VerilogHDL』を用いて解説しており、かなり実用的な内容となっています。
本の内容としては、以下のイメージです。
・デジタル回路を学ぶべき理由
・基本の論理
・組合せ論理回路
・順序回路
・プログラミング言語を用いた論理設計
・コンピューターを作ってみる
最後に、『マイコンを用いた簡単なコンピュータの作り方』についても触れていますが、ここは初心者には難しいかもしれません。

実際の設計方法を解説している参考書は少ないため、貴重な1冊です。
オススメ参考書④:ディジタル回路設計とコンピュータアーキテクチャ
マイクロプロセッサの作成を通じて、『マイクロプロセッサの構造(アーキテクチャ)を分かりやすく解説』した1冊です。
『デジタル回路』と『アーキテクチャ』が基本からしっかり解説されていました。
第1章 ゼロからイチへ
第2章 組み合わせ回路設計
第3章 順序回路設計
第4章 ハードウェア記述言語
第5章 ディジタルビルディングブロック
第6章 アーキテクチャ
第7章 マイクロアーキテクチャ
第8章 メモリシステムとI/Oシステム
付録A ディジタルシステムの実装法
付録B MIPS命令
付録C C言語プログラミング
特に『アーキテクチャ』について詳細に解説してあるため、『コンピュータアーキテクチャ』を学びたい方にオススメです。
また、『理解を深めるための演習問題やプログラム記述例』が豊富であり、非常に参考になります。

アーキテクチャについてここまでまとまっている書籍があまりないため、貴重な参考書です。
オススメ参考書⑤:FPGAの原理と構成
『FPGAの原理』を解説した珍しい1冊です。
FPGAは『ソフトウェアでハードウェアを記述できる』という特徴があり、近年世界中で注目されています。
しかし、『FPGAの原理』を日本語で解説した本は少ないため、貴重な参考書です。
1章 FPGAを理解するための基本事項
2章 FPGAの概要
3章 FPGAの構成
4章 設計フローとツール
5章 設計技術
6章 ハードウェアアルゴリズム
7章 PLD/FPGAの応用事例
8章 新しいデバイス,アーキテクチャ
『FPGAの過去から未来まで』解説してあり、飽きることなく読み進められました。
ただし、この本だけでプログラミング言語は理解できません。
そのため、『別の参考書でプログラミング言語の勉強』をすれば、FPGA全体の理解が深まると思います。

『FPGA未経験者』にぜひ読んで欲しい1冊です。
★【2024最新版】FPGAのオススメ入門書 5選 を紹介します!
困っている人 FPGAについて勉強したい。 オススメの参考書ってどれ? こんな要望に応えます。 FPGAを初めて学ぶ方の中には『どうやって勉強を進めていくべきか悩んでいる方』も多いと思います。 […]
オススメ参考書⑥:CPUの創りかた
CPUの作成を通じて、『CPUの動作原理を分かりやすく紹介した名著』です。
この本を読み、実際に『4bitのCPU』を制作している方も多く、ネットで検索すると多くの記事が見つかります。
本の内容としては、以下となります。
1 はじめの一歩のその前に
2 LED
3 デジタル回路の基礎の基礎
4 リセットとクロック回路
5 ROMを作る
6 CPUの設計準備
7 1bitCPU(らしきもの)
8 ALUとプログラムカウンタ
9 命令デコーダ
10 全回路図
11 動作確認
CPUを作成せずに読むだけでも、『デジタル回路の基礎』がしっかりと身に付くと思います。(私自身も制作はしていない)
学生時代、ソフトウェア専攻だった私にとっては『目から鱗』であり、『ハードとソフトの中間地点』をしっかり理解できました。

マイコン等を使用する回路設計者には、是非とも読んで頂きたい1冊です。
デジタル回路でオススメの本まとめ

今回は、『デジタル回路でオススメの6冊』をご紹介しました。
・ なっとくするディジタル電子回路
・ ゼロから学ぶディジタル論理回路
・ ディジタル回路設計とコンピュータアーキテクチャ
・ FPGAの原理と構成
・ CPUの創りかた
いかがでしたでしょうか。
デジタル回路設計は非常に難しく、途中で心が折れることもあります。
今回紹介した参考書を読めば、勉強のスタートダッシュが上手くいき、順調にデジタル回路を理解できるようになります。

気になった本を1冊でも読んで頂き、皆さんのお役に立つことを願っています。
\現役の回路設計エンジニアが解説!/
人気記事 【2024最新版】電子回路でオススメの本 7選を紹介します!
人気記事 【2024最新版】電子回路のオススメ通信教育 3選を紹介します!