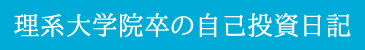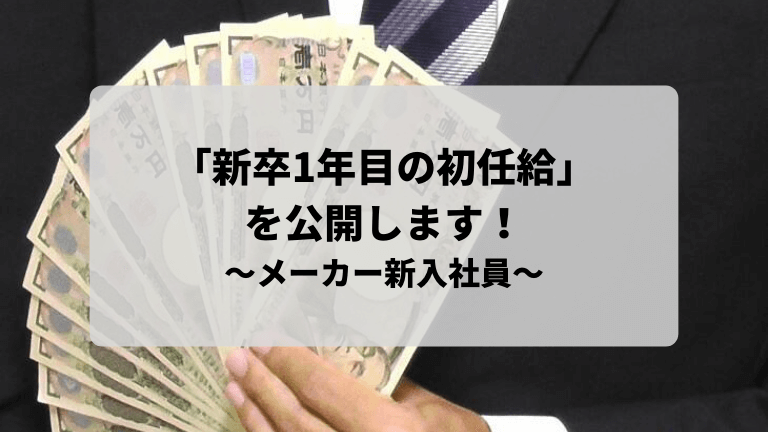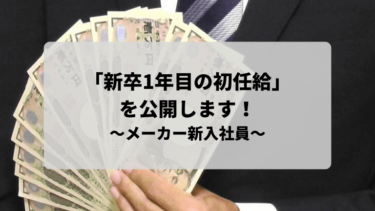もうすぐ社会人になる。
初任給の手取り額はどれくらいなんだろう。
こんな疑問を解消します。
私は大学院を卒業し、『大手自動車部品メーカー』で働いています。
先月ついに、初任給が振り込まれました!
私が就職した会社は5月から支給であるため、やっと初任給が貰えました。
『4月は給料が貰えなかった』ため、それまでは極貧生活で苦しかったです。

初任給が5月支給の会社に就職される方は、入社前に20万円ぐらい貯金することをオススメします。
そこで今回は、『理系大学院卒で大手自動車部品メーカーに就職した私自身の初任給』を公開します!
・ 所得税
・ 住民税
・ 社会保険料
・ 雇用保険料
・ 会社の保険
・ 初任給の明細を初めて見た感想
初任給の明細
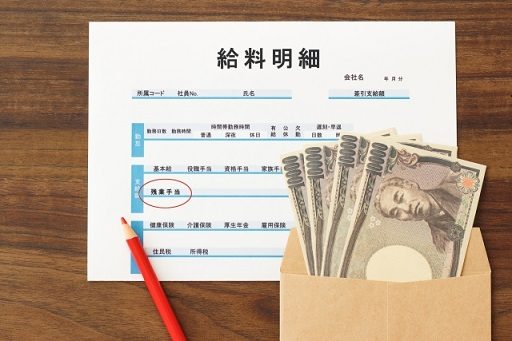
それでは、明細を発表します!
| 支給金明細 | |
| 基本給 | 230,000円 |
| 残業代 | 2,300円 |
| 合計 | 232,300円 |
| 控除金明細 | |
| 雇用保険料 | 800円 |
| 健康保険料 | 9,600円 |
| 厚生年金保険料 | 27,500円 |
| 所得税 | 4,600円 |
| 住民税 | 0円 |
| 会社の保険 | 5,600円 |
| 合計 | 48,100円 |
| 差引支給額 | |
| 差引支給額 | 184,200円 |
『支給金23.2万円』に対して、『控除金4.8万円』となりました。
4月は研修中だったため、『残業1.15時間』のみです。
初めてこの明細を見た時、思わず大きい声が出てしまいましたね…
「控除金高すぎるだろ!!」
こんなに税金や保険で取られてしまうんですね。

悔しかったので、所得税などについて調べました。
所得税

毎月源泉徴収される所得税を、どうやって算出しているか気になったので調べてみました。
源泉徴収税額は、通常なら『国税庁が毎年告示している税額表を適用して算出する』ようです。
しかし、給与計算を電子計算機などの事務機械によって処理を行っている場合は、財務省が告示している計算式により算出できるものとする特例が設けられています。
*国税庁『電算機計算の特例について』

2つの方法で計算してみたら、少し差異があったよ。
どちらかが損をするんじゃない?

最終的にその差異は年末調整で精算されるため、どちらかが損するといことはありません。
うちの会社は事務機械によって処理を行っているらしく、『電算機計算の特例』の計算式によって所得税が計算されています。
計算式を載せるのは大変なのでここには書きませんが、自分で計算してみたら数字がピッタリ合いました。
気になる方は弥生さんのサイトを参考にして計算してみて下さい。

新入社員で扶養家族がいない場合は、『給与支払い額×約2%』となります。
住民税

『入社1年目は住民税が0円』であり、2年目から課税されます。
なぜなら、『前年度の所得合計をベースにしてに翌年の納税額が決定される』ようになっているからです。
住民税については、年間の総所得から給与所得控除の65万円と基礎控除の約35万円を足した約100万円を差し引いて算出した所得が課税対象になります。

前年度は学生であり年収100万円を超えなかった私は、今年度は住民税が0円なのです。
『前年度にバイトで年収が100万円を超えた方』は、入社初年度から住民税が掛かります。
社会保険料(健康保険と厚生年金保険)
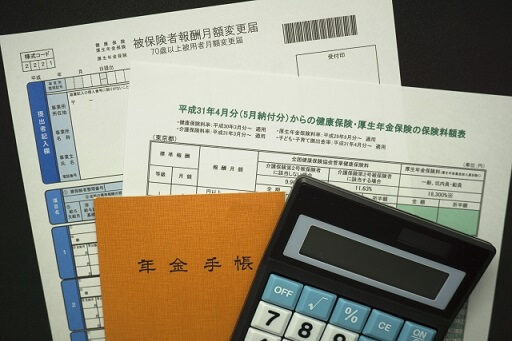
社会保険料は『標準月額報酬』によって決まります。
標準月額報酬の算出方法は、以下の通りです。
毎年7月に4月、5月、6月の3ヵ月間に支払われた給与支給額の平均額を「標準報酬月額表」の等級区分に当てはめて決定する。
これを『定時決定』と言います。
そして、9月から翌年の8月までの間は、標準月額報酬で決まった社会保険料を支払わなければなりません。

「4月、5月、6月」に残業を多くすると、1年間の社会保険料が高くなってしまうんです。

けど、新入社員は前年度働いていないし、この方法では標準月額報酬が決めれないんじゃない?
そうなんです。新入社員は前年度の給与実績がないため、別の方法で決まります。
『資格取得時決定』という方法です。
新入社員は資格取得時決定で算出

資格取得時決定の算出方法は、以下の通りです。
入社時の段階で4月に働いたら貰える給与を見積もり、標準報酬月額表に当てはめる。
「初任給」「毎月貰えるであろう通勤費手当」「残業代」を見積もるだけです。
なお、『資格取得時決定で決まった社会保険料はその年の8月まで適用』されます。

そして、9月からは定時決定で計算された社会保険料が適用されるのです。
健康保険料と厚生年金保険料の概算

健康保険料と厚生年金保険料の目安は、下記の通りです。
健康保険料:標準月額報酬の約5%
厚生年金保険料:標準月額報酬の約9%
詳細な額は、標準月額報酬を「会社を管轄する都道府県の保険税率表」と照らし合わせることによって分かります。

都道府県の保険税率表は、全国保険協会のHPに載っているので参照して下さい。
雇用保険料
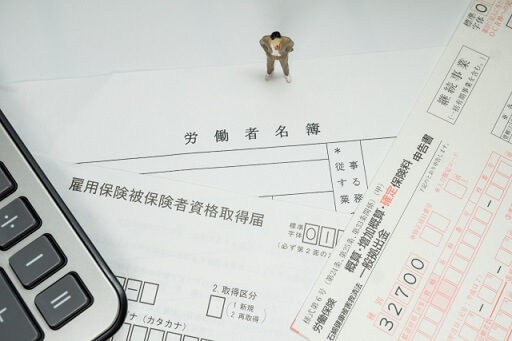
雇用保険料は、『給与支払い額×0.3%』となっています。
ただし、農林水産・清酒製造事業・建設事業以外の場合です。
私の場合、給与23万円+通勤手当3万円の『約26万円×0.3%=約800円』となります。

年間で考えると、約1万円です。
会社の保険
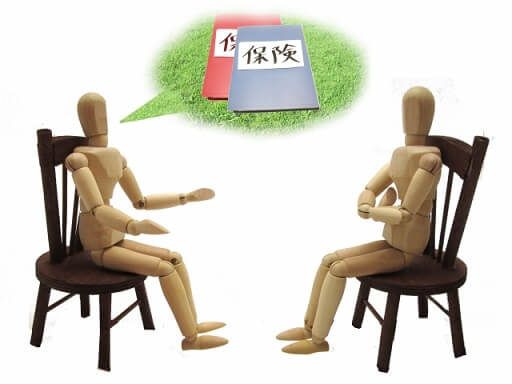
会社の保険は、県民共済とかの会社バージョンと考えてもらえれば良いです。

加入は任意なのですが、私はお得だと思ったので加入しました。
大企業は従業員数が多いため、このような保険に関しては割安になっています。
しかし、『保証が最低限で問題なければ、県民共済等の方が圧倒的に安い』です。
初任給の明細を初めて見た感想

初任給の明細を初めて見た『率直な感想』は以下の通りです。
「手取り額が思ってたよりも少ない…」
さらに、手取り額から寮費なども引かれるため、『実際に手元に残るのは約14万円』です。
自動車を所有すれば「車検費用」「自動車税」「保険料」もかかるので本当にカツカツ…

メーカーなら、修士卒の初任給はどこもあまり変わりません。
大学院卒なら、2年目からは大幅に昇給する

しかし、ここで朗報です!
『院卒なら2年目に役職が1つ上がる』ため、基本給が3万円ほど増えます。

また、研修期間が終われば残業もあるため、手取り30万円も見えてくるでしょう。
30歳くらいまでは我慢

『大手自動車部品メーカーは年功序列』であるため、確実にグングン上がっていきます。
お金を貯めたいなら、30歳くらいまでは独身寮や社宅に入って頑張りましょう。

年収なども暴露しているため、ぜひ他の記事も読んで下さい!
\新入社員の年収・残業など/
人気記事 【メーカー新入社員】新卒1年目の年収を公開します!
人気記事 【2024最新版】新入社員にオススメの本 10選を紹介します!