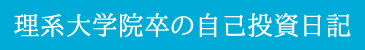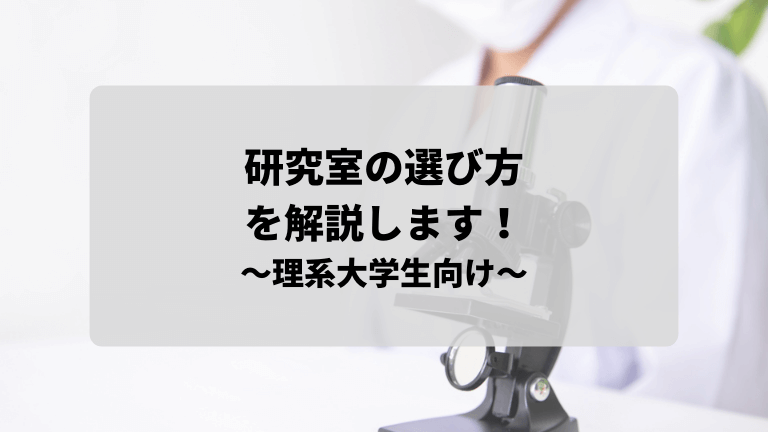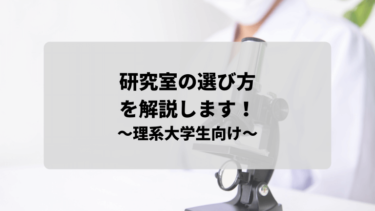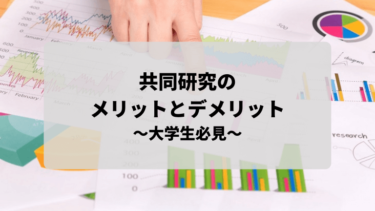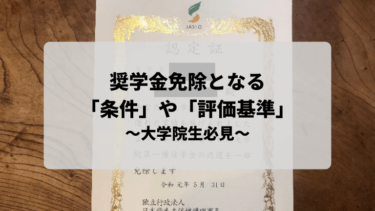そろそろ研究室を選ばなくちゃいけない。
「研究室を選ぶ際のポイント」が知りたい。
こんな疑問を解消します。
私自身、工学系の研究室に3年間在籍していました。

その結果、選ぶ研究室によって「就活の有利性」が異なることを知りました。
そこで今回は、『就活で有利になる研究室の選び方』を解説していきます。
1.企業との共同研究
2.研究テーマの決まり方
3.チームで研究を行っているか
・ 研究室次第で奨学金免除ゲット
研究室を選ぶポイント

研究室を選ぶ際は、以下3つのポイントをチェックしてください。
1.企業と共同研究をしているか
2.自分で新たに研究テーマを考えるか
3.チームで研究を行っているか
特に、『1.企業と共同研究をしているか』は、メリットが大きいです。

では、1つずつ説明していきます。
1.企業との共同研究

研究室訪問をしてみると、「企業と共同研究を行っている研究室が多い」ことが分かります。
ただし、教授や准教授だけではなく、『学生も参加して企業と共同研究を行っていることが大切』です。
共同研究のメリットは、以下の2点が挙げられます。
メリット①:特別なインターンや選考が受けられる
メリット②:ES(エントリーシート)を作成する際のネタが豊富になる
ありがたいことに、『特別ルート』に乗ることもできるのです。

詳しく解説していきます。
メリット①:特別なインターンや選考が受けられる

所属する研究室が企業と共同研究を行っていると、そのパイプで特別インターンに参加できたり、本就活で特別選考を受けられたりすることがあります。
私の研究室も多くの企業と共同研究を行っており、そのコネで入社した先輩や同期が沢山いました。

誰でも知っている自動車メーカーや電機メーカーに特別ルートで入社できるのです。
メリット②:ESを作成する際のネタが豊富になる

就活の選考時にES(エントリーシート)を作成する際にも、書くネタが豊富になります。
企業と共同研究を行えば、『世代や立場が異なる人と協力して何かをやり遂げた経験』が得られるからです。

採用する企業側は、このような経験を重要視してきます。
企業との共同研究については下記で紹介しているため、ぜひご覧ください。
\共同研究のメリット・デメリット↓/
困っている人 企業との共同研究って大変なイメージがある。 けど、そのおかげで就職活動が有利になるのかな? こんな疑問を解消します。 私自身、『大学4年生~大学院2年生』までの3年間に、企業と共同研究を行い[…]
2.研究テーマの決まり方

研究室によって「研究テーマの決まり方」は異なります。
1.論文を沢山読み、自分で新たに研究テーマを考える
2.先輩の研究を引き継ぐ
大きく分けてこの2つとなります。

就活という観点では、「1.論文を沢山読み、自分で新たに研究テーマを考える」がオススメです。
どちらが就活に有利になるのか

「2.先輩が行っている研究を引き継ぐ」方が、研究は容易に進みます。
論文を書いたりする際に、先輩のデータがそのまま使えるからです。
しかし、『1.論文をたくさん読み、自分で新たに研究テーマを考える』方が就活で有利になります。

理由を説明していきましょう。
新たな価値を生む力

理系出身学生の多くが就職するメーカーは、求める人物像に『新たな価値を生む力』のキーワードを含んでいます。

メーカーは新しい製品を作り続ける必要があるため、「新たな価値を生む力」を重要視するのです。
では、それぞれの「研究テーマの決まり方」で「新たな価値を生む力」がどのように評価されるか考えてみましょう。
⇒自分で試行錯誤して新たなアイデアを実践してみようと研究を進めたため、「新たな価値を生む力」があることをアピールしやすい
⇒自分で試行錯誤して新たなアイデアを考えたわけではないため、「新たな価値を生む力」があることをアピールしにくい
以上から分かるように、『自分で新たに研究テーマを考え、自分で考えて進めた』ことの方が高く評価されやすいのです。

面接時には「なぜそれを選んだのか」「どうしてその方法を思いついたか」など、自分でどのように進めたかひたすら深堀されます。
共同研究の場合はどちらの決まり方が多い?

企業と共同研究の場合は、『先輩が行っている研究を引き継ぐ』方が多いです。
ただし、共同研究であっても自分で関連分野の論文を読み、「学生自らが提案して研究を進める」研究室もあります。

企業と共同研究を行い、なおかつ学生自ら提案して研究を進めることがベストですね。
3.チームで研究を行っているか

仕事は単独では進められないため、『他人と協力して仕事を進める力』が就活では重要視されます。
そのため、「チームでプロジェクトを進めた経験」が得られる『チームで研究を行っている研究室』の方が就活で有利になるのです。

また、チームで研究を行っていれば、必ず先輩と仲良くなります。
そうすると、ESや面接などの選考情報を教えてもらうこともできます。
『就活は情報戦』であるため、この点も非常に重要です。
研究室次第で奨学金免除ゲット

『できるだけ論文が多く書けるようなテーマ』を選びましょう。
共同研究の場合、守秘義務のせいで研究成果を論文にできないこともあるため、共同研究先を選ぶ際はその点も教授などに聞いておきましょう。
なぜ論文が多く書けるようなテーマを選ぶ必要があるか。それは、『大学院生は奨学金が免除されやすいから』です。

大学院生は「親の年収が関係ない」ため、学部時代には親の年収制限で借りられなかった人でも借りられます。
全額免除されれば『211万円』、半額免除でも『105万円』がゲットできます!
詳しくは下記で紹介しているので、是非ご覧ください。
\奨学金免除の条件・評価基準↓/
悩んでいる人 大学院では奨学金が免除されやすいらしい。 免除となる「条件」や「評価基準」が知りたい。 こんな疑問を解消します。 なんと本当に『大学院で借りる奨学金は全額免除または半額免除されやすい』のです[…]
研究室の選び方まとめ

いかがでしたでしょうか。
『研究室の選び方によって就活の有利性が異なる』ため、ぜひこの記事を参考にして下さい。
この記事が皆さんのお役に立つことを願っています。
\共同研究のメリット・デメリットなど/
人気記事 【院試】数学でオススメの参考書 17選を紹介します!
人気記事 【院試】電磁気学でオススメの参考書 7選を紹介します!