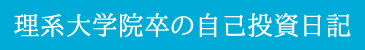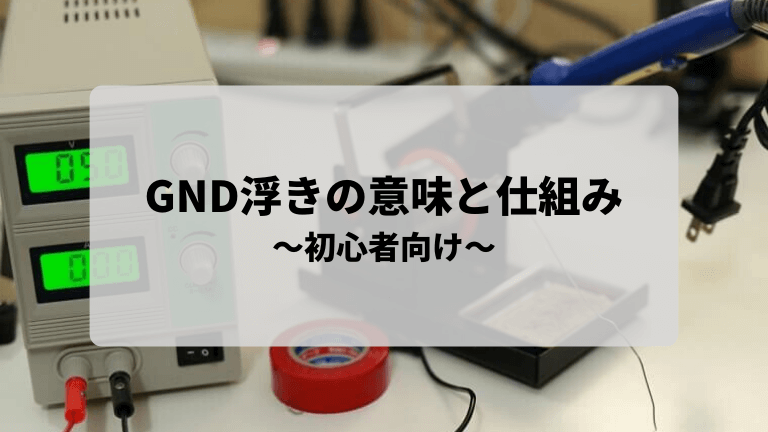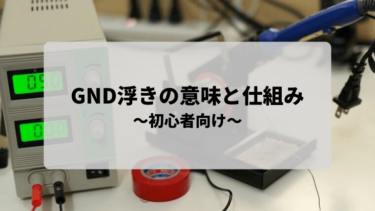電子回路で「GND浮き」という用語がよく出てくる。
どんな意味なんだろう?
こんな疑問を解消します。
GND浮きとは、『GND電位が0Vでなくなること』を意味します。
グランド電位が0Vでなくなるとは、『グランド電位より高くなること』『グランド電位より低くなること』の両方を指します。
そこで今回は、『GND浮きの意味・仕組み』について解説していきます!
・ 車載製品の電子回路GND
・ GND浮きの仕組み
・ 車体ボディー間のGND浮き
・ まとめ
★【2023最新版】回路設計の年収は?現役エンジニアが解説します!
困っている人 回路設計に興味がある。 年収はどれくらいなの? こんな疑問を解消します。 回路設計エンジニアは『経験を積めば1,000万円も狙える職業』です。 トヨタ自動車やキーエンスなど、多[…]
GND浮きとは
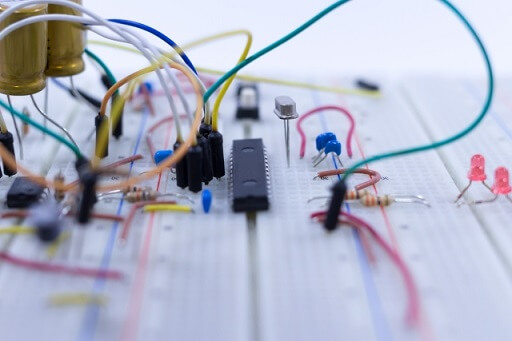
GND浮きとは、『GND電位が0Vからズレてしまうこと』であり、自動車の電気回路では必ず考慮されています。
本来、GND電位は0Vですが、電位が上下してしまうため、設計エンジニアは『GND電位のズレ幅』も考慮して回路設計しなければなりません。

それでは続いて、『なぜGND浮きが発生してしまうのか』解説していきます。
車載製品の電子回路GND

自動車には、多くの電子回路が搭載されています。
そのため、全ての回路から『電源バッテリーのマイナス端子』まで配線を引くことはできません。

全ての電子回路から電源バッテリーまで配線を引けば、凄まじいスペースを取りますからね。
そこで、『電源バッテリーのマイナス端子を車体のボディーと接続し、各電子回路のGNDをボディーに接続する』ことでGNDをまかなっているのです。
GND浮きの仕組み

ボディーは金属であるため、もちろん『抵抗成分』があります。
そのため、『ボディーから電源バッテリーのマイナス端子まで電流が流れる際に電圧降下が発生する』のです。

電圧降下が発生するということは、ボディーと『電源バッテリーのマイナス端子』は電位が異なりますね。
この電位差が『GND浮き』です。
車体ボディー間のGND浮き

『ボディー間でも電圧降下によって電位が異なる』ことに注意しなければなりません。
各電子回路のGNDが接続されているボディーは位置が異なるため、車体ボディー間のGND浮きも考慮する必要があるのです。
例えば、マイコンGNDとSW入力部GNDで考えてみましょう。
SW入力部GNDよりマイコンGNDの方が電源バッテリーに近い場合、電流が流れる経路は以下のようになります。
SW入力部GND → マイコンGND → 電源バッテリー
その場合、電位の高さは以下となります。
SW入力部GND > マイコンGND > 電源バッテリー

このように、回路によって『GNDの電位』が異なるのです。
GND浮きの意味・仕組みまとめ

いかがでしたでしょうか。
電子回路設計者にとって『GND浮きは必須の知識』です。
GND浮きの意味・仕組みをしっかりと理解しましょう。
\現役の回路設計エンジニアが解説!/
人気記事 【2023最新版】回路設計の年収は?現役エンジニアが解説します!
人気記事 【2023最新版】電子回路設計者にオススメの資格 6選を紹介します!