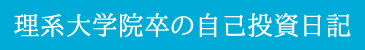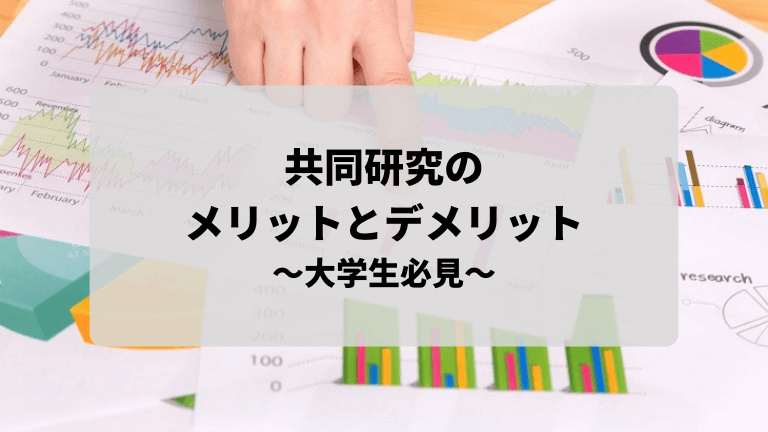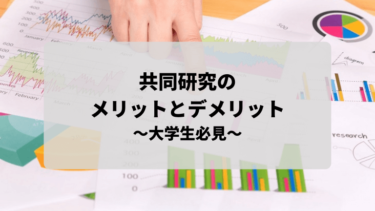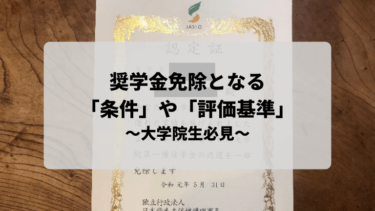企業との共同研究って大変なイメージがある。
けど、そのおかげで就職活動が有利になるのかな?
こんな疑問を解消します。
私自身、『大学4年生~大学院2年生』までの3年間に、企業と共同研究を行いました。
その結果、以下のことを実感しました。
・共同研究は意外と楽
・共同研究によって就活が有利になる
そこで今回は、私自身が感じた『共同研究のメリット・デメリット』を紹介していきます。
・共同研究のデメリット 2つ
共同研究のメリット

共同研究のメリットは、下記の4つとなります。
1.研究テーマを自分で考えなくて良い
2.研究室宛の説明会、特別インターンシップ・特別選考がある
3.ES(エントリシート)を作成する際のネタが豊富になる
4.研究が半強制的に順調に進むため、論文を出しやすい
どれも素晴らしいメリットですが、特に「4.論文を出しやすい」は『奨学金免除に繋がる』ので重要です。

では、1つずつ説明していきます。
1.研究テーマを自分で考えなくて良い

研究テーマの決まり方は、大きく分けて以下の3つとなります。
1.所属する研究室の研究分野に関連した論文を多く読み、自分で新たに研究テーマを考える
2.卒業する先輩が行っている研究を引き継ぐため、最初から研究テーマが決まっている
3.企業がやりたい研究テーマが教授に依頼され、その研究テーマが学生に割り振られる
共同研究の場合、『企業がやりたい研究テーマが教授に依頼され、その研究テーマが学生に割り振られる』で研究テーマが決まります。
そのため、自分で研究テーマを考える必要がなく、『研究の背景や目的・有用性も企業が示してくれる』のです。

それに対して、共同研究でない場合は、自分で新たに研究テーマを決めるため、配属後しばらくは論文を読む日々が続きます。
その中から『他に誰もやっていなく、しかも有用性があるような研究テーマ』を自分で考え出さなければなりません。
2.研究室宛の説明会、特別インターンシップ・特別選考がある

所属研究室が共同研究していると『共同研究先の企業から特別配慮を受ける』ことが多いです。
・研究室宛の特別説明会
・特別インターンシップ
・本就活での特別選考
私自身が所属していた研究室も、多くの企業と共同研究を行っており、『コネで特別な説明会』が多くありました。

共同研究先の特別インターンに選考なしで参加できたり、就活解禁前に選考してもらっていた先輩や同期も多かったです。
しかも、誰でも知っている『大手自動車メーカー』や『大手電機メーカー』です。
3.ES(エントリシート)を作成する際のネタが豊富になる

就活の書類選考時には、まずES(エントリーシート)という応募書類を企業に提出しなければなりません。
そのESには、『自己PR』や『学生時代に頑張ったこと』を記入する欄がほぼ必ずあります。

共同研究を行っていれば、自己PR・学生時代に頑張ったことをESに記入する際に、書くネタが豊富になります。
例えば、共同研究を通して『世代や立場が異なる人と協力して何かをやり遂げた経験』が得られます。
どんな仕事でもそうですが、特にメーカーは多くの関係者と協力して仕事を進めなければなりません。
そのため、『世代や立場が異なる人と協力して仕事を進める力』が必要となるのです。

このような能力を持つ学生を、採用する企業側は高く評価しています。
4.研究が半強制的に順調に進むため、論文を出しやすい

共同研究の場合、研究進歩について『定期的に企業と打ち合わせ』があります。
そのため、毎回成果を出さなければならないので半強制的にですが、研究は順調に進みます。
結果として、『成果を論文として頻繁に出しやすくなる』のです。

基礎研究であるため、守秘義務があって外部に公開できない共同研究先もありますが、大半の企業は論文を書くことを推奨してくれます。
論文を出すと、奨学金免除が狙える


論文って大変そう。
論文を出すと何か良いことがあるの?
論文を多く出すことのメリットは、『奨学金が免除されやすくなる』ことです。
学部生は親の年収制限がありますが、大学院生は親の年収制限がありません。

そのため、学部時代に借りることができなかった人でも大学院では奨学金を借りることができます。
全額免除で『211万円』、半額免除でも『105万円』が免除されます。
詳しくは下記で紹介しているので、是非ご覧ください。
\奨学金免除に興味がある方はこちらへ↓/
悩んでいる人 大学院では奨学金が免除されやすいらしい。 免除となる「条件」や「評価基準」が知りたい。 こんな疑問を解消します。 なんと本当に『大学院で借りる奨学金は全額免除または半額免除されやすい』のです[…]
共同研究のデメリット

共同研究のデメリットは、下記の2つとなります。
1.研究テーマを自分で考えていないため、「新しい価値を生む力」の点で就活の際に不利になる
2.定期的に打ち合わせがあるため、学生らしい海外への長期旅行や語学留学ができない
凄まじいメリットに比べれば小さなデメリットですが、しっかり把握しておきましょう。

では、1つずつ説明していきます。
1.研究テーマを自分で考えていないため、「新しい価値を生む力」の点で就活の際に不利になる

就活時、多くの企業の求める人物像に『新しい価値を生む力』というキーワードが含まれています。

なぜ「新しい価値を生む力」が重要視されているの?
多くの理系学生が志望するメーカーは、人々の生活をより豊かにするため、新しい価値を生み出さなければなりません。
そのため、「研究テーマを企業から決められて進めた」ことよりも「自分で新たに研究テーマを考え、自分で考えて進めた」ことの方が高く評価されます。

面接時には「なぜそれを選んだのか、どうやってその方法を思いついたのか」等、自分で物事を進めたかどうか深堀されるのです。
就活を有利にしたいなら、『共同研究でも自分で関連分野の勉強を行い、自ら提案して研究を進める』ようにしましょう。
そうすれば、共同研究のメリットである「世代や立場が異なる人と協力して何かをやり遂げた経験」と同時に「新しい価値を生む力」も就活時にアピールできます。
2.定期的に打ち合わせがあるため、学生らしい海外への長期旅行や語学留学ができない

実は、週1回しか研究しなくてもよい「とても緩い研究室」も存在します。
緩い研究室であれば、研究はあまりせずに好きなことをして過ごすことができるため、海外への長期旅行や語学留学も可能です。
しかし、『就活面接であまり研究をしていないことがバレてしまう』ため、就活が不利になるデメリットがあります。

それに対して共同研究の場合、月に一度ほど定期的に打ち合わせがあるため、長期旅行や語学留学は難しいです。
共同研究のメリット・デメリットまとめ

・研究テーマを自分で考えなくても良い。
・特別選考を受けられる。
・ESを作成する際のネタが豊富になる。
・論文を出しやすい。
・研究テーマを自分で考えていないため、「新しい価値を生む力」の点で就活の際に不利になる。
・しかし、自分で関連分野の勉強を行い、自らが提案して研究を進める工夫を行えば、そのデメリットも解消できる。
いかがでしたでしょうか。
企業と共同研究するメリットは数多くあり、必ず就活の際にプラスになります。

ぜひ共同研究をしている研究室を選んで下さい。
院試・大学院生向けのオススメ記事

『院試・大学院生向けの有益情報』を、下記で紹介しています。
大学院出身である、私自身の実体験をベースにした記事ばかりです。
院試前の大学生・現役大学院生の皆さんは、ぜひご覧ください。
・ 【院試】電子回路でオススメの参考書 3選を紹介します!
・ 【大学生必見】基本情報技術者で就職が有利になった体験談
・ 【大学院生必見】奨学金免除となる「条件」や「評価基準」を解説します!
・ 【2024最新版】研究室の選び方を工学部出身が徹底解説します!
・ 【2024最新版】理系大学生にオススメの本 12選を紹介します!
大学生・大学院生ならPrime Studentがオススメ

「Prime Student」は、Amazonプライムの学生版です。
月額300円で下記の特典が利用できます。
お急ぎ便が無料
Prime Video見放題
Prime Music聴き放題
Prime Readingで電子書籍読み放題
Amazon Photosで写真保存し放題
本最大10%ポイント還元
『無料期間が6ヶ月間もある』ため、試しに登録してみると良いでしょう。

詳しくは下記で紹介しているため、ぜひご覧ください。
\Prime Studentの特典・口コミなど↓/
困っている人 Prime Studentがお得ってよく耳にする。 入会するべきか判断するため、値段・特典・対象者が知りたい。 こんな要望に応えます。 学生の中には、『Prime Studentを利用すべきか分[…]